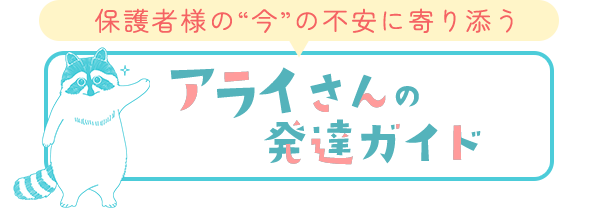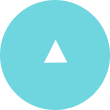「療育って遊んでるだけじゃないの?」保護者が知っておきたい本当の意味
療育の様子を観察していて「遊んでいるだけで意味があるの?」と不安に感じる保護者様は少なくありません。実際、療育では遊びが活用されています。療育に遊びが必要な理由や育つスキル、家庭でも可能な療育遊びを紹介します。
「遊び」って本当に療育?その意味と背景
療育における遊びの役割
「遊び」は、単なる楽しみの時間ではなく、発達を支える重要な活動です。遊びは、社会性やコミュニケーション能力を育む場となります。例えば、友達と一緒に遊ぶことで、順番を守る、協力する、感情を表現するなどのスキルが自然と身につきます。問題解決能力や柔軟な思考が養われるというのもメリットです。また、脳・神経発達の観点から見ると、遊びは神経回路の形成に寄与します。特に乳児期から幼児期にかけて、遊びを通じて五感を刺激することで、脳内の神経細胞(ニューロン)間の接続点である「シナプス」が増加し、神経回路が強化されます。この時期の遊びは、感覚や運動能力の発達にとって欠かせないものです。
「ただ遊んでるだけ」に見える理由とその誤解
「ただ遊んでいるだけ」に見える原因は、外見だけではその意図や効果がわかりにくいからです。療育の現場では、遊びを通じて子どもの発達を促すための計画的なカリキュラムが組まれています。例えば、積み木遊びは手先の器用さや空間認識能力を養い、順番を守る遊びでは社会性や自己制御力を育むことが目的です。一見すると自由遊びのように見えても、専門的な観察と目的意識のもとで行われており、子どもの発達段階に応じた支援が行われています。
遊びから育つスキルとは?具体例で見る療育の効果
ジェンガ
積み木を慎重に取り出し、バランスを保ちながら積み上げていく過程で、手先の器用さや集中力、空間認識能力が育まれます。ジェンガは、細かな動作を繰り返すため、手指の巧緻性が向上する遊びです。積み木の配置やバランスを考えることで、空間の把握力が高まります。また、複数人で遊ぶことで、順番を待つ、協力する、ルールを守るといった社会的スキルが育成されます。
トランポリン
跳ぶ動作を通じて体幹が強化され、姿勢の安定性やバランス感覚が向上する遊びです。四肢の協調性を高めることで運動能力全般の発達にもつながります。跳躍による体の揺れや空間認知を通して感覚情報の統合が進み、感覚統合能力も養われます。また、順番を守る、ルールを守るといった社会的スキルや注意力の向上も期待でき、お子さんの多面的な発達に有効です。
リズムウォーク
音楽やリズムに合わせて歩くことで、リズム感が養われ、体幹の強化やバランス感覚の向上にもつながります。また、リズムに集中して動くことで集中力が高まり、集団で行う場合には他者との協調性も育まれます。リズムウォークは楽しみながら体や心の多面的なスキルを伸ばすことができる、重要な療育手段です。
絵カード
絵カードは、物や出来事を簡単なイラストや写真で表現したカードで、コミュニケーションや生活スキルの向上に役立つ視覚的支援ツールです。言葉の理解や表現に課題があるお子さんに特に効果的とされています。毎日のルーチンを絵カードで示すことで、子どもは次に何をすべきかを視覚的に理解しやすくなり、支度や行動のスムーズな移行が期待できます。また、絵カードは感情の認識や表現にも活用可能です。顔の表情や状況を描いたカードを使うことで、子どもは他者の気持ちを理解し、自分の感情を適切に表現する練習ができます。
家でもできる療育遊び
ふれあい遊び
「ふれあい遊び」は、親子の絆を深め、子どもの発達を促す効果的な活動です。手遊びや歌遊び、タッチ遊びなど、身体的な接触を伴う遊びを通じて、情緒の安定やコミュニケーション能力の向上が期待できます。特別な道具や広いスペースを必要とせず、家庭で簡単に取り入れることができる遊びです。
感触遊び
「感触遊び」は、粘土や布、スポンジなど異なる質感の素材に触れる遊びです。触覚の発達が促され、物の違いを認識する力が育まれます。また、手や指を使った操作を通じて、細かな運動能力や手先の器用さも向上します。お子さんの好奇心を引き出し、日常生活での適応力を高めるのにも有効です。
粘土遊び
手や指を使って粘土をこねたり丸めたりする動作は、手先の器用さを養い、脳の発達にも有用です。粘土の感触や色、形を楽しむことで、触覚や視覚の感性が育まれます。自由な創作活動を通じて、想像力や集中力、問題解決能力も向上します。
言葉あてゲーム
言葉あてゲームは、家庭で楽しみながらお子さんの語彙力や思考力を育む療育遊びです。例えば、50音表を使って「いちごはどこ?」と問いかけ、子どもに該当するイラストを指さしてもらいます。この遊びは、視覚的な認識力や注意力を高めるとともに、言葉と物の関連性を理解する力を育みます。物の特徴を尋ねる応用問題を加えることで、抽象的な思考力や記憶力も向上します。
すごろく
サイコロを振って進むゲームは、順番を待つ、ルールを守る、勝ち負けを受け入れるといった社会性や情緒のスキルを育むのに適しています。サイコロを振る動作やコマを進める手先の運動は、運動機能や集中力の向上にも有効です。ゲームの内容を工夫することで、言語理解や記憶力、問題解決能力など、認知面の発達も促進できます。親子で一緒に遊ぶことで、コミュニケーションの機会が増え、信頼関係の強化にもつながります。
子どもに合った療育を見つけるためにチェックしたいこと
担当者・カリキュラムの専門性を見極める
療育において遊びは重要ですが、変化を感じられないこともあります。不安を解消するには、専門性を見極めることが重要です。専門性が高い事業所では、発達障害に関する知識や支援技術を持つスタッフが、個別のニーズに応じたプログラムを提供しています。特性や成長段階に合わせた適切な支援が可能なため、効果的な療育が期待できます。
施設のスタイルの違いを知る
施設によって、個別支援と集団支援、親子参加型と子ども単独型など、支援のスタイルが異なります。例えば、個別支援では一人ひとりの特性に合わせた支援が可能ですが、集団支援では社会性や協調性を育むことができます。また、親子参加型では保護者が支援に関与しやすく、子ども単独型では自立心を養うことができます。自分の子どもの特性や家庭の状況に最適なスタイルを選ぶことで、より効果的な支援が期待できます。
早めの情報収集と体験
多くの施設では見学や体験利用を受け付けており、実際の雰囲気や支援内容を直接確認できます。活用することで、施設のスタイルやスタッフの対応などを把握することができ、適切な選択が可能です。また、早期に情報を収集することで、希望する施設の空き状況や利用開始時期なども把握でき、スムーズな利用開始につながります。お子さんの特性や家庭の状況に最適な施設を見つけるために、早めの行動が大切です。