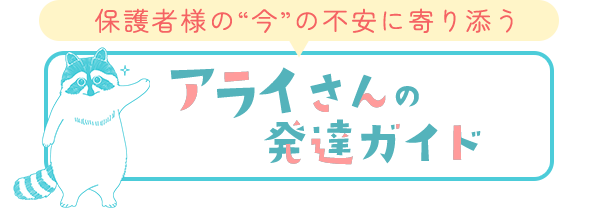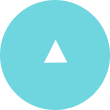3歳児がじっとしていられない、多動について
はじめに
3歳――それは「歩く・話す・遊ぶ」が一気に複雑化し、目に映るものすべてが“実験材料”になるダイナミックな時期です。
好きな場所へ俊敏に移動できる筋力と、興味を次々切り替える知的好奇心が合わさり、親や保育者から見ると「とにかくじっとしていられない」「落ち着きがまるでない」と感じてしまうケースも多々あります。
しかし、その行動は未熟さではなく発達途上ゆえの自然な姿である場合も多く、焦りや怒りだけで向き合うと、子どもの自己肯定感を傷つけたり、親子関係の摩耗につながりかねません。
3歳の“多動的”なふるまいを①発達段階の視点②環境・心理要因③発達障害の可能性に分けて整理し、家庭・園・専門機関それぞれで実行できる具体策を詳述します。
3歳児がじっとしていられない典型シチュエーション
- 飲食店で席を立ち歩き回る
- スーパーや商店の陳列棚を触りたがる、走り出す
- 公共交通機関で大声で歌ったり、床に座り込む
- 園行事の最中に教室を出て廊下を探検
- 食事・着替え・歯みがきの途中でおもちゃへ一直線
これらは「待つ」「選ぶ」「抑える」といった自己調整機能がまだ発達途中であることを示します。3歳児は“いま・ここ”への没入度が高く、「もうすぐ順番が来る」「終わったら楽しいことがある」という先の見通しを言語的に保持することが難しいです。
視覚・聴覚などの感覚刺激に対して脳が情報を取捨選択するフィルタリング機能が未熟なため、周囲の物音や光景に注意を簡単に奪われます。
そもそも3歳は“動いて学ぶ”年齢
運動欲求のピークが到来
身長や体重の増加とともに大きな筋群が発達し、転がる・跳ぶ・回るといった全身運動が脳の前頭前野や小脳を刺激します。
これにより認知機能の成熟が促されるため、子ども自身が本能的に“動きたくて仕方がない”状態になります。
感覚統合がまだ未熟
感覚統合とは、視覚・前庭覚・固有受容覚など複数の感覚情報を脳内で整理し、適切な運動や行動を選ぶプロセスです。
統合が不完全な時期は、身体を頻繁に動かすことでフィードバックを得てバランスを取ろうとするため、多動に見えやすくなります。
自己主張=自我の芽生え
「イヤ!」「自分で!」が多発する第一反抗期では、選択権を奪われたと感じただけで癇癪が爆発しやすくなります。感情コントロールも未完成なため、興奮すると行動が加速度的に激しくなります。
こうした発達的背景を理解すれば、行動を一律に“わがまま”や“しつけ不足”と断じる危険性に気づけるでしょう。
落ち着きがない主な原因を多角的に分析する
横にスクロールできます
| カテゴリ | 具体的要因 | 見分け方のヒント |
|---|---|---|
| 発達的要素 | 自己調整力・感覚統合の未熟さ | 同年齢でも個人差が大きいが、月齢が進むにつれ着席時間が延びる傾向 |
| 環境的要素 | 騒音・まぶしい照明・人混みなど過剰刺激 | 静かな部屋や照明を落とした空間では落ち着きやすい |
| 心理的要素 | 不安・緊張・親のイライラを感受 | 家庭内トラブルや転園直後など急変イベント後に顕著 |
| 生活習慣 | 睡眠不足・高糖質の間食・運動不足 | 休日にたっぷり寝た翌日は比較的穏やか、など日内変動を観察 |
| 医学的要素 | 鉄欠乏・甲状腺機能異常・ADHDなど | 眼の下のクマや極端な疲労感があれば小児科受診を検討 |
原因は単独ではなく重層的に絡み合うことがほとんどです。
まずは行動が出やすい時間帯・場所・前後の出来事を観察し、家庭内で簡易記録をつけると要因の切り分けが容易になります。
ADHDを含む発達障害の可能性
ADHDとは
注意欠如・多動症(ADHD)は、不注意・多動・衝動性が年齢相応の水準を大きく上回り、日常生活や学業・対人関係に支障をきたす神経発達症です。
遺伝的要因が強く、脳内ドーパミンの調節不全が関与すると考えられています。
3歳で見られる兆候
- 着席指示が届かず、家庭・園・公共の場で一貫して離席が多い
- 指示を聞く前に行動し、危険物や車道へ飛び出す衝動性
- 周囲の子よりも眠りが浅い・入眠が遅い
- 興味対象が秒単位で変わり、遊びを完結させずに転々とする
診断基準上、3歳未満での確定診断は慎重に行われ、主に5~6歳で複数の専門家による評価が推奨されます。
すぐに診断名を求めるのではなく、専門家と経過を共有しながら見守る姿勢が早期支援の近道です。
いますぐできる対処法6つ
-
見通しを可視化する
タイムタイマーや絵カードで「残り3分」「終わったら公園」を示し、子どもの頭の中の時計をサポートします。 -
動⇔静のリズムを設計する
朝イチに公園で全身運動、午前中は机上活動、昼食後はお昼寝タイムなど、活動と休息を交互に取り入れます。 -
感覚刺激を調整する
椅子の脚にゴムバンドを巻き、足でキックできるようにしたり、噛んでよいシリコンチューブを持たせたりして軽微な刺激を提供。 -
スモールステップと成功体験を積む
「30秒座れたらシール1枚」「5枚集めたら好きな絵本を読む」など短い目標を設定して達成感を与えます。 -
公共の場での応急対応を準備する
壁側の座席を確保し、窓の景色を実況したりお気に入りヘッドホンで音を遮断するなど、安心できる“逃げ場”を設けます。 -
生活リズムと栄養を見直す
就寝時刻は20:00~21:00を目安にし、朝食でタンパク質や鉄分をしっかり摂取。砂糖やカフェインは午後遅くに避けることで多動が軽減するケースがあります。
親の接し方5箇条
- 共感ファースト:子どもの感情に寄り添い、「ワクワクしてるんだね」と代弁する。
- 一貫したルール:許容範囲を日によって変えず、タイマーやシール表で見える化する。
- 肯定7:指摘3のバランス:良い行動への賞賛を70%以上心がける。
- クールダウンスペース:毛布やぬいぐるみを置いた安全な一角を設ける。
- 親のセルフケア:家族や友人に預ける時間を確保し、心の余裕を維持する。
園・保育者との連携
- 事前共有:連絡帳やアプリで「切り替えに弱い」「大きな音が苦手」など具体的情報を伝える。
- 合理的配慮:前列より後列、出入り口近くの席へ移動、活動指示は視覚補助を併用する。
- 共同作戦会議:月に一度、担任と面談して家庭と園で同じ支援手法を共有する。
一方的な要望ではなく、「家庭ではこうしたら上手くいった」「園ではどうですか?」と双方向でアイデアを交換する姿勢が重要です。
専門機関へ相談するタイミング
- 行動によるケガや事故が月に数回以上発生する
- 家族が育児疲れや睡眠不足、抑うつ状態に陥る
- 友だちとのトラブルが増え、加配保育士を勧められた
- 保健師や園から経過観察・専門受診を勧告された
主な相談先
- 市区町村の発達支援センター/こども相談センター
- 小児神経科・児童精神科
- 臨床心理士・公認心理師が在籍する療育施設
- 親の会・ピアサポートグループ(SNSや自治体掲示板で検索)
早期の相談は「診断名を付けるため」ではなく、「子どもに合った学び方・遊び方を見つけるため」の第一歩です。
よくあるQ&A
Q1:叱れば治りますか?
A:大声で止めても一時的に行動が止まるだけで自己調整力は育ちません。むしろ叱られる自分というネガティブ自己概念が強化される恐れがあります。
Q2:テレビやタブレットは悪影響?
A:30分以内・保護者と対話しながら視聴する共同注視なら語彙や社会性にプラス。長時間・ひとり視聴は興奮度を高めるので避けましょう。
Q3:甘えさせすぎでは?
A:3歳の抱っこ要求は安心基地を再充電する行為。適切に応じることで自立へのエネルギーが満たされます。
Q4:薬は必要?
A:日本でのADHD薬物療法は原則6歳以上。3歳ではまず環境調整と行動療法が優先されます。
まとめ
3歳児の「じっとしていられない」行動は、脳と体が急成長する証であり、感覚統合や自己調整力を獲得する過程で起こる発達の産物です。
- 発達段階・環境・心理など多面的な要因をまず観察し記録する
- 見通しを示し、感覚刺激を調整し、成功体験を重ねる具体的対処法を実践する
- 園や専門機関と早期に連携し、親自身もサポート資源を活用する
子どもが自分の体と心をハンドル操作できるまでには時間がかかりますが、適切な関わりと支援で確実に伸びていきます。焦りすぎず、一歩ずつ親子のペースでステップアップしていきましょう。