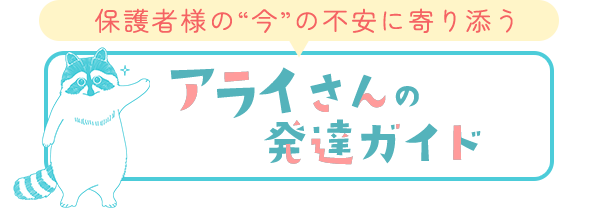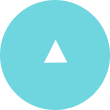特別支援学級に入る基準について
発達障害児が特別支援学級に通うこともできる?
発達障害のあるお子さんが小学校に入学するにあたり、保護者様にとっては通常学級と特別支援学級のどちらを選ぶべきかは頭を悩ませる問題でしょう。お子さんに合った進路先を検討するためにも、特別支援学級と通常学級との違い、特別支援学級ではどんな指導が受けられて、どのようなメリット・デメリットがあるのか把握しておくことが大切です。
ここでは、特別支援学級と通常学級についてそれぞれ紹介しながら、お子さんの進路先を選ぶ際のポイントもまとめています。
特別支援学級とは
特別支援学級とは、比較的軽度の障害がある生徒に対し、きめ細かな教育を行うために設置された学級です。
通常学級との違いとしては、1クラス8名定員の少人数で、1人ひとりのニーズや困りごとに合わせた支援を行えるという点があげられます。特別支援学級の対象となるのは、知的障害や肢体不自由、病弱・身体虚弱、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害を持つ生徒です。
特別支援学級に入れるかどうかは、障害の有無や程度をはじめ、お子さんの状態や校内・地域の体制、お子さん本人や保護者様の意向などをもとに、市区町村の就学支援委員会が総合的に判断します。学校や地域によっては特別支援学級の枠が限られていて、サポートを最も必要としているお子さんが優先される場合もあるようです。
特別支援学級の指導内容
特別支援学級では、生徒1人ひとりに合わせた特別な指導を受けることができます。特別な指導としては「自立活動」があり、以下の6項目の中から生徒にとって必要な項目を検討し、具体的な指導を行いながら自立を促していくのが特徴です。
【自立活動の項目】
- 健康保持
- 心理的安定
- 人間関係の形成
- 環境の把握
- 身体の動き
- コミュニケーション
また、学校教育の一環として、通常学級に通っているお子さんと活動を共にする「交流及び共同学習」が行われることも。交流及び共同学習の具体例としては、学校行事や部活動、自然体験活動などがあります。交流及び共同学習を通して、特別支援学級の生徒の自立と社会参加を促し、さまざまな人と助け合い支え合って生きていくことを学ぶのが目的です。
特別支援学級のメリット
特別支援学級をお子さんの進路先に選ぶメリットとしては、少人数クラスで障害種別に学級が編成されるため、お子さんの能力や特性に合わせたカリキュラムで学習できることです。お子さんに必要な指導や支援を受けられるのは、通常学級にはない大きなメリットと言えるでしょう。
特別支援学級のデメリット
お住まいの地域によっては近くの学校に特別支援学級が設置されておらず、遠くの学校に通学しなければいけないことも。また、通常学級と違って他者と関わる機会が少ないため、一般社会に出たときに必要となる集団生活や社会性を学ぶのが難しいというデメリットもあります。そのほかにも、通常学級と特別支援学級を行き来することにより、お子さんがストレスを感じる場合もあるので注意が必要です。
特別支援学級卒業後の進路
小学校を特別支援学級で卒業した場合の進路を考える際、選択肢として候補にあがるのが「中学校でも特別支援学級に入る」「通常学級に変更する」「特別支援学校に入学する」の3つです。
高校には特別支援学級が設置されていないため、中学校を特別支援学級で卒業した場合の進学先としては、公立・私立の高校や技能連携校、専修学校、特別支援学校が候補としてあげられます。もしくは就職を検討する場合もあるでしょう。
文部科学省が発表した令和5年度の学校基本調査によると、中学校の特別支援学級卒業者(30,385人)のうち、高等学校等に進学したのは約58%(17,760人)、特別支援学校は約36%(10,960人)、専修学校(高等課程)は約1.5%(443人)、公共職業能力開発施設等は約0.1%(38人)、就職は約0.8%(228人)となっています。
参照元:文部科学省「学校基本調査 / 令和5年度 初等中等教育機関・専修学校・各種学校 卒業後の状況調査 卒業後の状況調査票(中学校)」 https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/kekka/k_detail/2023.htm
通常学級とは
通常学級とは1つのクラスを1つの先生が担当するスタンダードなクラスで、定型発達のお子さんと一緒に授業を受けるのが特徴です。
通常学級のメリット
定型発達のお子さんと同じ教室で集団生活を送ることになるため、社会生活により近い環境を経験できます。集団で物事に取り組めるので達成感を味わえたり、集団生活を通して社会性をはぐくめたりできるのも通常学級のメリットです。
また、公立校であれば、発達障害のあるお子さんやその保護者様から学習環境を調整してほしいという申し出があった場合、特性や困りごとに配慮する合理的配慮が義務付けられています。どの程度対応してもらえるかは学校側との合意形成が必要にはなりますが、通常学級でもお子さんの特性に合わせて配慮してもらうことは可能です。
通常学級のデメリット
公立校の通常学級でも学習環境についてある程度は配慮してもらえますが、必要最低限になってしまうので、特別支援学級ほどの対応は望めません。担任の先生が発達障害に詳しくない場合は、必要な支援ができないこともあるでしょう。また、お子さんが学習についていけなかったり、クラスメイトとうまく関係を構築できずに孤立したりトラブルを起こしたりする可能性もあります。
ひどいケースだといじめに発展することもあるので、通常学級への進学は慎重に検討する必要があるでしょう。
お子さんの進路先を選ぶ際のポイント
お子さんに必要な支援・配慮事項をまとめる
お子さんに合った進路先を選ぶには、お子さんの今の状況を十分に理解し、どこなら必要な支援が受けられるのかを検討することが大切です。
そのためにも、お子さんの状況や特性を把握したうえで、必要な支援や配慮してほしい事項を整理してまとめましょう。必要な支援や配慮してほしい事項を整理する際は、お子さんが通っている幼稚園・保育園や療育施設の職員、医療機関などにも相談してみることをおすすめします。自宅以外でのお子さんの様子を聞いたり、専門家の観点から必要な配慮をアドバイスしてもらったりすることで、適切な進路先を選ぶヒントになります。
地域にある学校の情報を集める
地域によって特別支援学級や特別支援学校、通級指導教室などの種類・数が異なるため、まずは自治体のホームページから近くにどのような学校や学級があるのかを調べてみましょう。お子さんが特別支援学級や通級に通っている保護者がまわりにいれば、どんな雰囲気か、必要な指導や支援が受けられそうかどうかなど話を聞いてみることをおすすめします。
見学に行く
地域にある学校や学級の情報を収集したら、実際に足を運んでみましょう。見学することで、学校や学級の方針・雰囲気がお子さんに合っているかどうかを直接確認できます。また、進路先を選ぶときの判断材料として、以下の点も確認しておくと良いかもしれません。
- 学校や教室全体の雰囲気
- 学級数や1学級あたりの人数
- 学習の進度
- お子さんがクールダウンできる場所の有無
- 支援級と通常学級の行き来
- 通常学級でのサポート体制
通級とは
通級(通級指導教室)とは、通常学級に在籍している生徒が、通級指導教室に通って障害に応じた特別な指導を受けることです。
在籍している学校に通級が設置されていない場合は、通級が設置された近隣の学校にその時間だけ通うことになります。通級の対象は軽度な障害を持つ生徒で、2006年から学習障害や注意欠陥多動性障害も通級の対象に加わりました。
通級を利用できるかどうかは、市区町村の教育委員会が専門家による障害の診断内容をはじめ、どの学校で通級による指導を行うのか、時間割や通学の面などから総合的に判断します。
インクルーシブ教育とは
インクルーシブ教育とは、障害の有無で区別せず、すべての子どもが同じ空間でともに学ぶことを目指した教育理念のことです。
日本の教育現場では、障害のあるお子さんは特別支援学級や特別支援学校で学ぶこととされてきました。一方で、インクルーシブ教育は障害を持つお子さんも、そうでないお子さんもすべての子どもが同じ空間でともに学ぶことを目指しています。
日本でもインクルーシブ教育を推進する動きが見られますが、環境整備が追い付いていなかったり、教員の特別支援教育に関する知識・技能が十分でなかったり、などの課題も残っています。