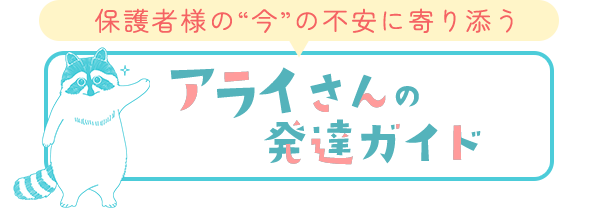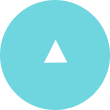発達障害のグレーゾーンて?

発達障害のグレーゾーンとは
発達障害は、主に自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠陥・多動症(ADHD)、学習障害(限局性学習症、LD)の3つに大別されます。
発達障害のグレーゾーンとは、これら発達障害の診断基準の全てを満たさないため、確定診断はつけられないものの発達障害の傾向があることを示すものです。
ただ、発達障害のグレーゾーンは、正式な診断名ではありません。
0~6歳では
発達の診断自体が難しい時期
0~6歳は、成長変化が著しい時期であるため、お子さんの言動や様子は時々刻々と変化します。
かんしゃくや強いこだわりも一時的なものとして成長とともに消えることもあるため、この時期に発達障害の確定診断はもちろん、グレーゾーンの判断をすることも容易ではありません。
自閉スペクトラム症は4~5歳、ADHDは5~7歳で診断がつき始めることがほとんどです。
その前の時期に、診断がつかないからと放置すれば、早期の適切な支援のタイミングを逸してしまうことにもなりかねません。
気になることがあれば、なるべく早めに相談した方が、お子さんや保護者のためになります。
自閉スペクトラム症/
自閉症スペクトラム障害(ASD)
についてもっと知る
注意欠如・多動症/
注意欠如・多動性障害(ADHD)
についてもっと知る
グレー=症状が軽い
ではありません
発達障害のグレーゾーンとは、診断基準の全てを満たさないものの、発達障害の傾向が認められる状態であり、決してその症状が軽いことを示しているのではありません。
確定診断がつかないことで安心してしまう部分もあると思いますが、適切な対応をしないと成長とともに発達障害の症状が顕著にあらわれ、失敗や挫折をくり返すことにより、二次障害をまねいてしまうこともあります。
二次障害とは
二次障害とは、発達障害という一次障害に対する無理解や適切な支援や対応がなされなかったことを主な原因として、生活や人間関係に行き詰まり、自尊感情や自己肯定感、自己有用感などに大きな歪みを生じてしまうことです。
不満や怒りの抑圧が内側に向けられた場合には、うつやひきこもり、不登校など、外側に向かった場合は、過度の反抗や暴言、暴力や非行を引き起こすことがあります。
お子さんからのSOS
このページを執筆したライターのkenさんは、児童福祉司として、非行や不登校、自傷行為や家庭内・校内暴力などのケースを扱う中で、二次障害にもがき苦しむ子どもたちに数多く出会ったそう。
そのときに思ったのは、「二次障害による問題行動を抑止することは容易なことでない」ということだったそうです。
できるだけ早い時期に気づき、適切な関わりや支援をしてあげることが、お子さんを二次障害で苦しませないために大切なことです。
もちろん、保護者様だけで対応していては、保護者様が疲弊してしまうので、専門家への相談や、療育を活用したり、同じ悩みを持つ保護者様のコミュニティで悩みを共有し合ったり、こころとからだを軽くする術をたくさん持っておいてください。